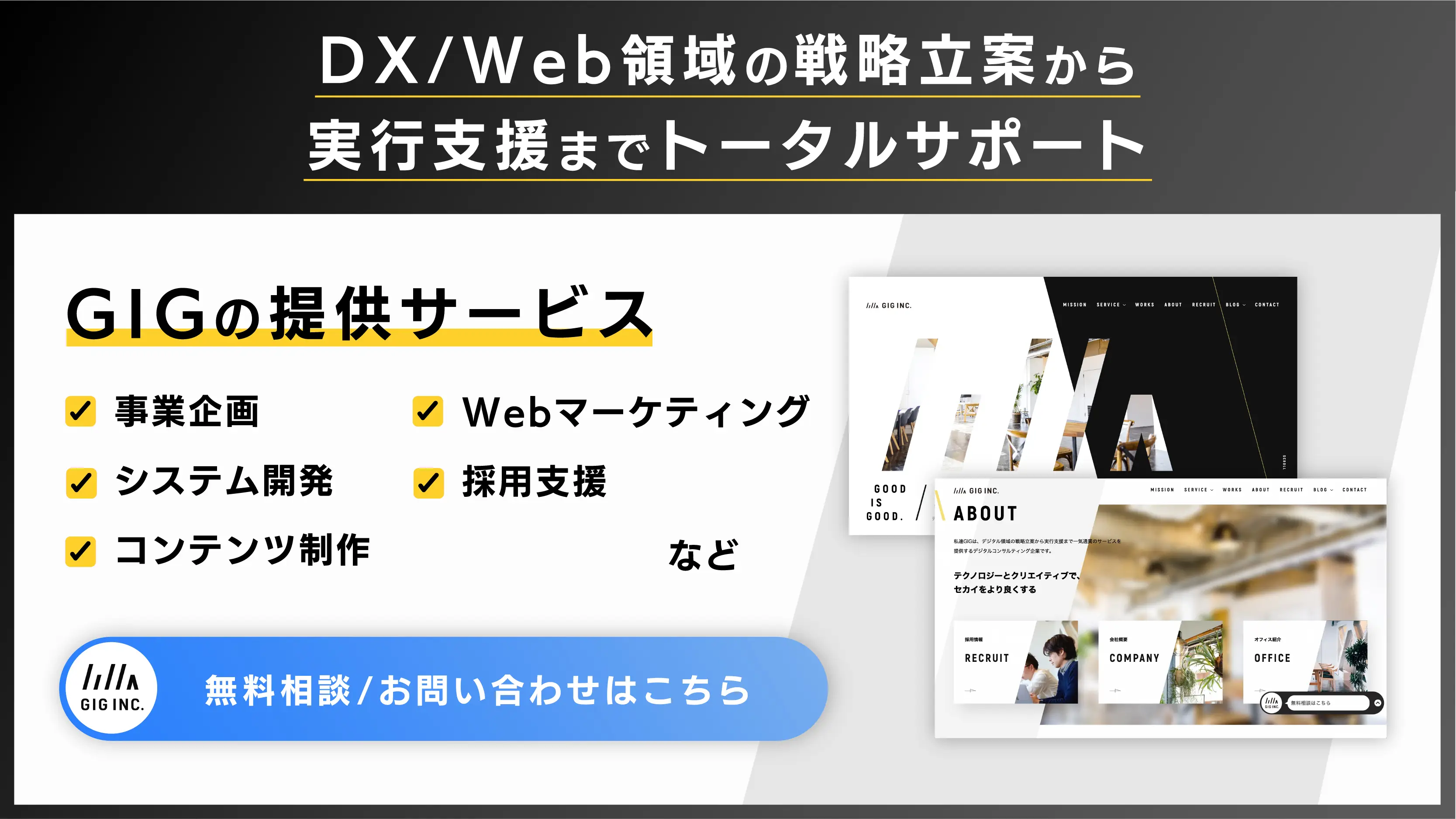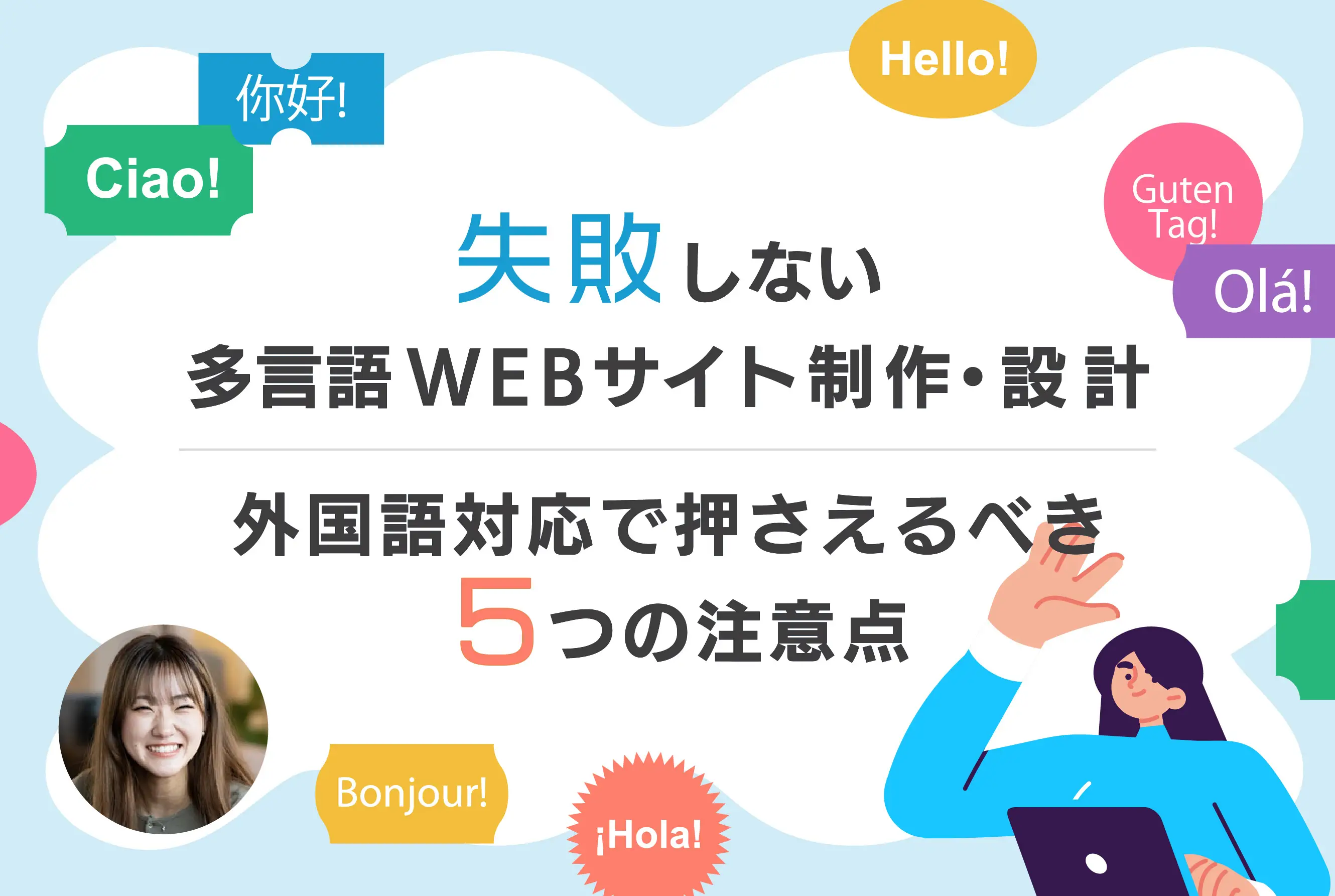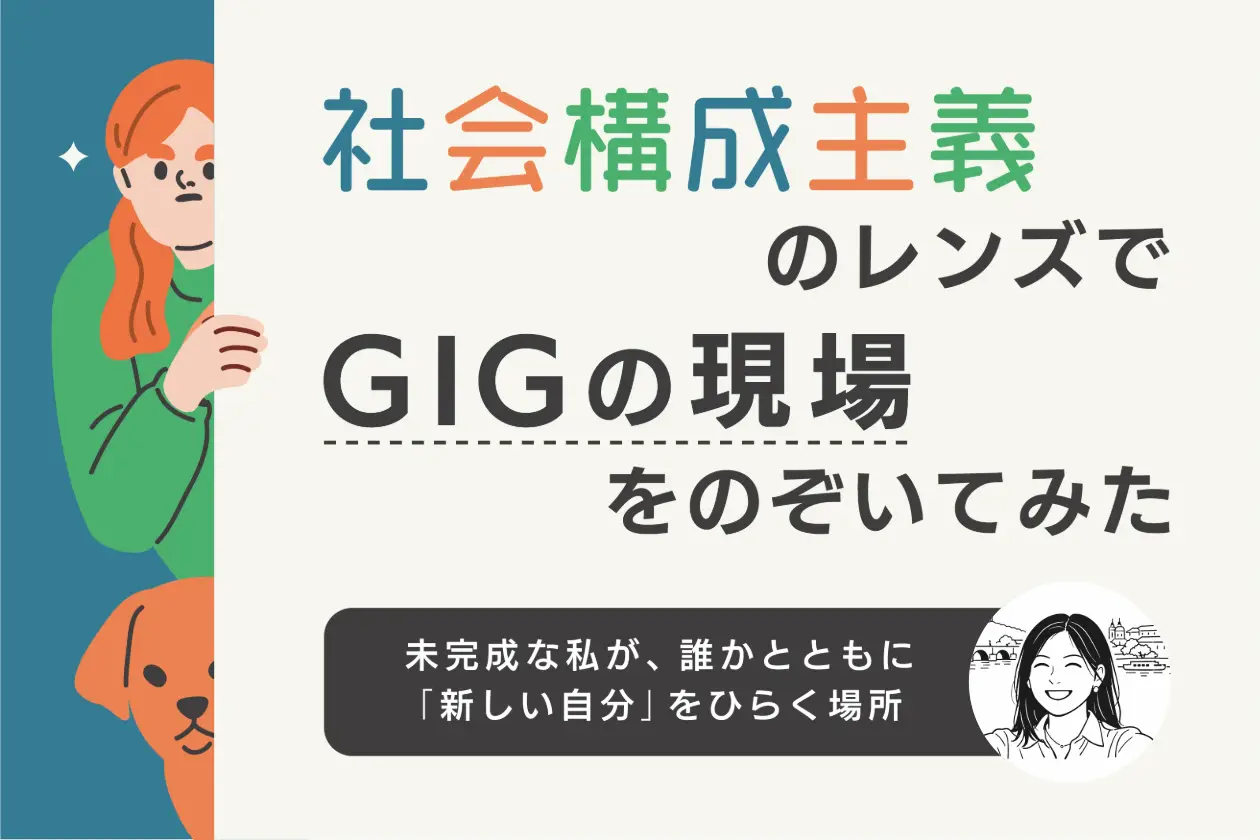インフラ構築の流れ/工程とは?ネットワークエンジニアが解説!|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG
BLOG
ブログ
インフラ構築の流れ/工程とは?ネットワークエンジニアが解説!
2022-06-12 制作・開発

情報化社会の昨今、さまざまな企業や店舗では多くのシステムが稼働しています。こうしたシステムの稼働に必要な基盤が「インフラ」です。
システムの基盤となるインフラ構築は非常に重要で、どんなに良いシステムでも、インフラ構築があいまいだと思った通りの動作をしてくれません。最悪の場合、システムのデータソース流出など、大規模な事故に繋がる可能性もあります。
そこで本記事では、ネットワークエンジニアの筆者がインフラ構築の具体的な流れを解説します。
インフラとは
インフラとはインフラストラクチャー(Infrastructure)の略で、「基盤」という意味を表します。インフラという言葉が使われる場合、生活基盤を指すことが多いため、インフラという言葉に出会ったら“生活に絶対必要なもの”と思えばわかりやすいでしょう。
生活に絶対必要なものとしては、公共施設や水道、ガス、電気などがインフラに該当します。そして昨今では「ネットワーク」も重要なインフラの一つです。
そのため、IT業界ではインフラといえば「ITシステムを支える基盤」のことを指す場合が多く、私たちが普段目にしているITシステムの裏には、必ずインフラが存在します。
そして、こうしたインフラは、ハードウェアとソフトウェアに分けることができます。
ハードウェア
ITインフラ、つまり一つのシステムが稼働するうえで必要となるハードウェアには、たとえば以下のものが挙げられます。
・ネットワーク機器
・サーバー
・パソコン
・ストレージ
・UPS(無停電電源装置)
サーバーとパソコンがネットワークを介してデータのやり取りを行い、バックアップ先としてストレージが用意されていて、非常用にUPSに接続されている。一つのシステムが稼働するうえで最低限のハードウェアを挙げるだけでも、これだけの数になります。
ソフトウェア
「システムを稼働させるためにソフトウェアが必要」と言われても、少しイメージがしにくいかもしれません。しかし、皆さんも日々触れているWindowsやMacなどのOSは、システムの基盤となる代表的なソフトウェアです。
サーバーやパソコンには、WindowsやMacOS、LinuxといったOSがインストールされ、そのOSを基盤としてアプリケーションが実行されるため、これもインフラに位置づけられます。
インフラ構築の業務内容
上記のようなインフラ構築を行うエンジニアを、インフラエンジニアといいます。インフラエンジニアは会社によって「ネットワークエンジニア」や「CE(カスタマーエンジニア)」などに分別されますが、どれもインフラの構築を担当するという点は同じです。
では、インフラ構築の際はどのような作業が必要になるのかを確認しましょう。
まず、サーバーの設置と設定を行います。クラウドサーバーを使う場合は契約だけで済みますが、オンプレミスで構築する場合はサーバーメーカーからサーバーを手配し、サーバー室に配置します。
次に、そのサーバーにUPSや電源、ネットワークなどを繋げていきます。サーバー室の作りによってはネットワークが分割されているなど、ネットワークの構造は企業によってさまざま。インフラエンジニアとは事前に入念な打ち合わせをするべきでしょう。
最後は、サーバー内にソフトウェアをインストールします。OSに関しては基本的に最初から入っていますが、アプリケーションを利用するために必要な、データベースなどのミドルウェアをインストールします。
ここまでの、アプリケーションを稼働できる状態にするための一連の業務が、インフラ構築作業です。
インフラ構築の流れ/工程
具体的にインフラエンジニアの仕事内容について解説しましたが、上記はあくまで発注側がインフラエンジニアに依頼を出してから、エンジニアがアプリケーションの導入をはじめるまでの流れとなります。
しかし、実際は発注側がインフラエンジニアに業務を発注するまでの流れや、インフラ構築が完了した後の流れも重要です。ここでは、インフラエンジニアに業務を発注する際の、エンジニアとのやり取りについて解説します。
1. 要件定義のために打ち合わせを行う
まずは、実際にシステムの導入を目的とした打ち合わせを行います。この打ち合わせが特に重要で、どのようなシステムをどのように導入することで、どういった費用対効果を生むのか。導入のためにはどのようなインフラを構築するのか、などを定義します。
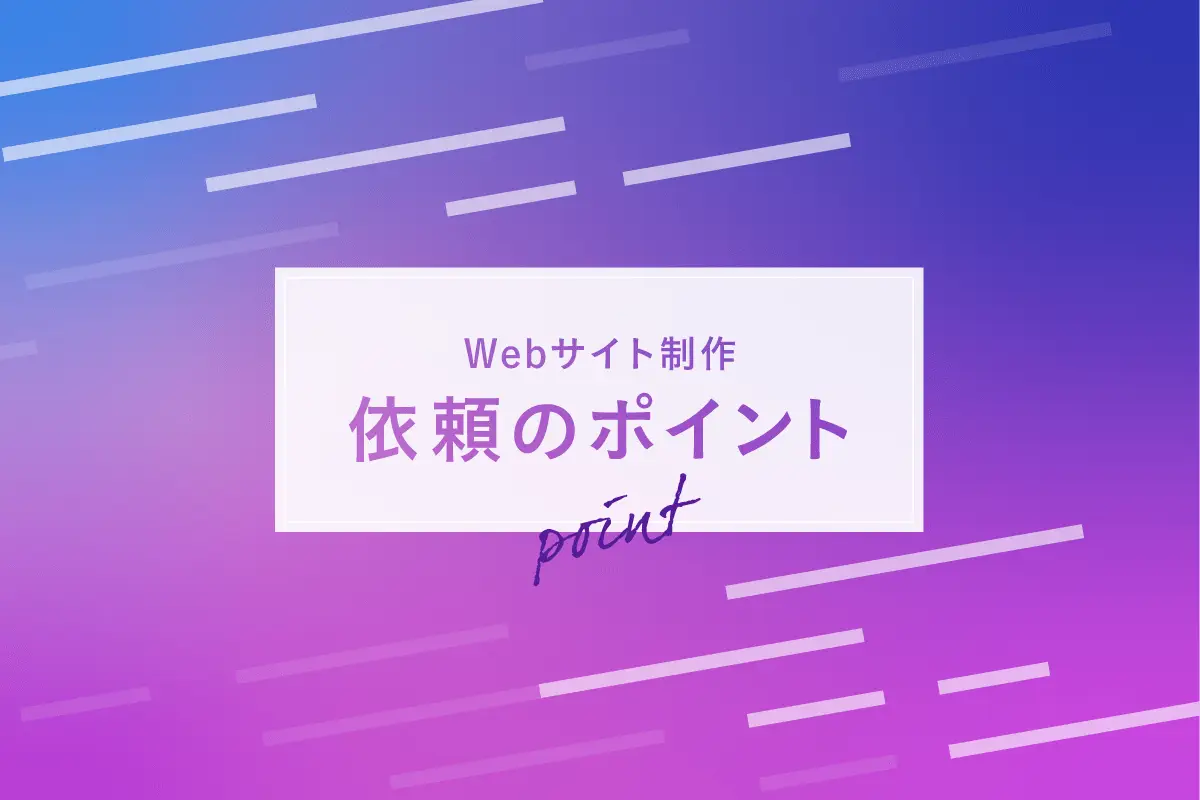
2. 要件を満たすインフラを構築する
要件が定義できたら、インフラエンジニアはインフラの構築を進めていきます。
インフラの構築作業の具体的な作業についてはすでに触れましたが、サーバー室などに入って作業を行う場合には、構築作業に失敗すると他のシステムにも影響をおよぼす場合があります。
発注側はインフラエンジニアの質問や意見などに耳を傾け、必要な情報は迅速に提供するようにしましょう。
3. 構築したインフラの動作確認を行う
インフラの構築が完了すれば、実際にシステムのインストールなどを行って本番同様のテストを実行します。
この際は、アプリケーションの動作検証チェック項目などを用意し、エンジニアが適切なテストをできる環境を整えましょう。
導入チームでの検証が完了すれば、次にクライアント側で動作確認を行います。
4. インフラ上で運用を開始する
クライアント側での動作確認およびテスト稼働期間が終われば、正式に運用がはじまります。しかし、インフラは構築して終わりではなく、ここから保守・運用フェーズに入ります。予期せぬ不具合やバグの発生はつきものなので、正式運用後も気は抜けません。
何か不具合やエラーが発生した際に、原因を素早く特定して解消できるよう、インフラの設計仕様書などはきちんと準備しておきましょう。
関連記事:「Webサイト保守」の費用相場はどれくらい?東京のWebサイト制作会社が解説
インフラ構築を行う2つの方法
インフラ構築作業は、おもに「自社で行う」または「外注する」のどちらかで実施されます。それぞれの方法について、概要やメリット・デメリットについて紹介します。
方法1. 自社の社内エンジニアでインフラを構築する
最も一般的な方法は、自社の社内エンジニアに依頼してインフラを構築する方法です。特に中〜大規模な会社では、インフラエンジニアとアプリケーション専用のエンジニアが分かれている傾向にあります。
メリットは社内エンジニアなので連携がとりやすく、進行状況などが確認しやすいこと、仕様変更などの修正などを依頼しやすいことが挙げられます。
しかし反対に、社内エンジニアの場合は作業が属人的だったり、新技術へのキャッチアップがいま一つだったりといったデメリットも考えられるでしょう。また、新たにネットワークエンジニアを雇う場合は採用・教育コストも馬鹿になりません。
方法2. インフラ構築を外注する
最近ではクラウドサーバーが普及してきたこともあり、インフラの構築作業を外注する企業が増えています。クラウドサーバーを活用することで、通常のサーバーと比べてベンダーは保守が楽になり、発注側も社内エンジニアでは扱えないような技術を専門としている業者に任せられるため、双方にメリットがあります。
課題としては、内部の機密事項などを外部に公開してしまうセキュリティリスクなどが考えられます。この懸念から外注に踏み切ることができない企業も存在するのが現状です。
なおGIGには、AWSをはじめとしたインフラ構築のスペシャリストが揃っています。セキュリティ対策もナショナルクライアントの求めるレベルに耐えられるものを用意。安心してご依頼ください。
関連記事:株式会社GIGがAWSのテクノロジーパートナーになりました!
インフラ構築・運用保守はGIGにお任せください
今回の記事では、インフラ構築作業の概要や手順について紹介しました。
GIGはWeb制作だけでなく、システム会社としてインフラの構築作業やシステム開発案件を数多く担当しています。過去の案件から培った、メディアサイトなどで起こりうるリスクを考慮したインフラ構築をサポートいたします。
無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
■サイト保守事例
三菱UFJIP - コーポレートサイト制作・多言語サイト制作
ミクシィ - コーポレートサイト制作 / デザイン・保守運用
トレタ - リクルートサイト制作 / システム開発 / インフラ保守
WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

GIG BLOG編集部
株式会社GIGのメンバーによって構成される編集部。GIG社員のインタビューや、GIGで行われたイベントのレポート、その他GIGにかかわるさまざまな情報をお届けします。