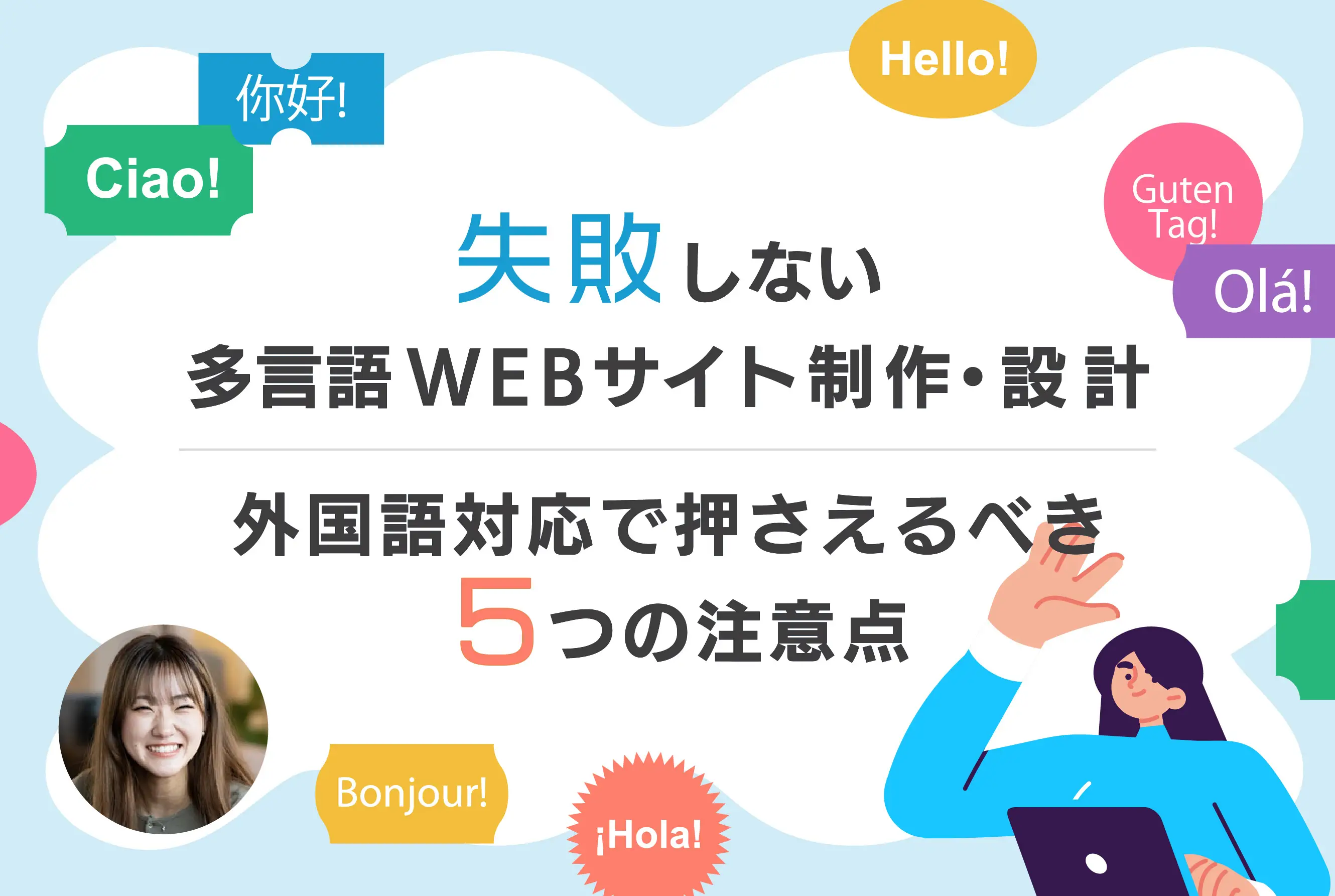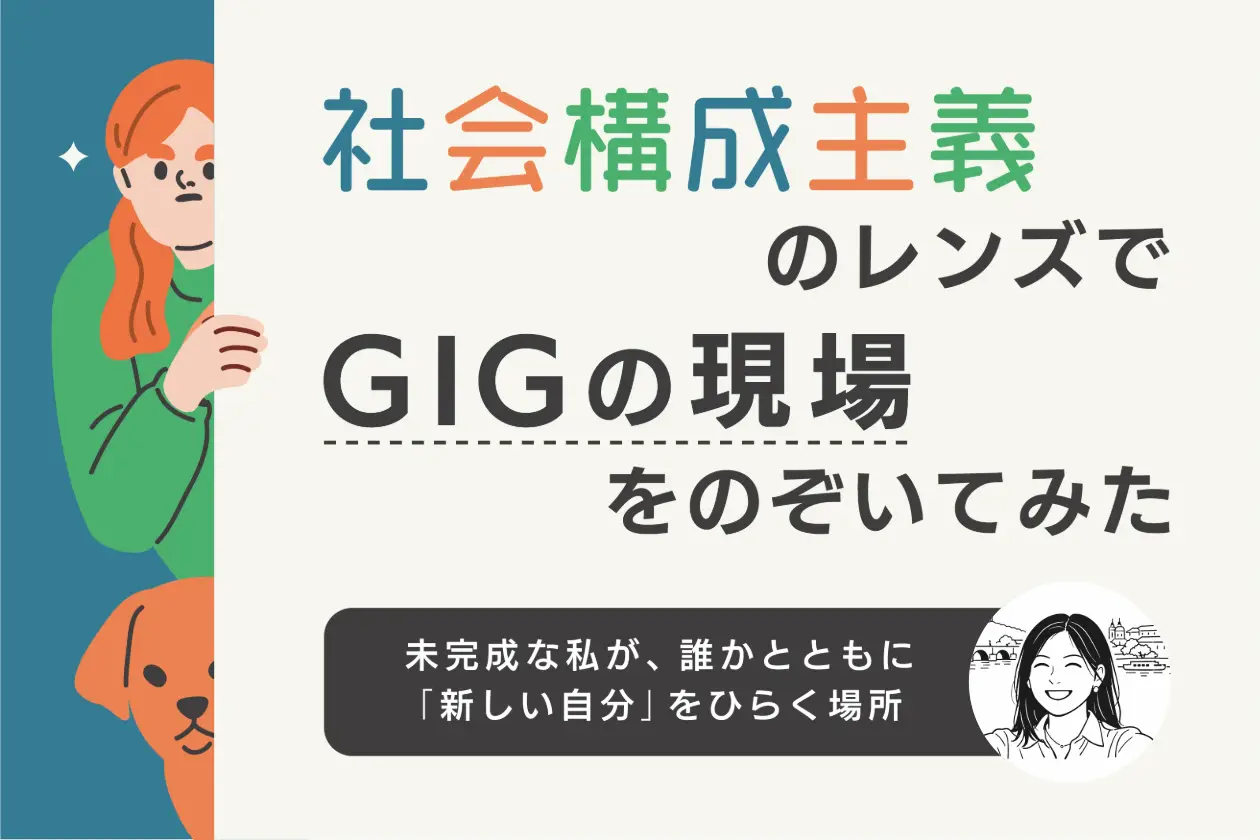Claude Codeを3ヶ月使ってわかった「できること・できないこと・できるようになること」|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG
BLOG
ブログ
Claude Codeを3ヶ月使ってわかった「できること・できないこと・できるようになること」
2025-09-26 制作・開発

こんにちは!商品開発部でエンジニアとして働いている成田です。普段は、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS・MAツールである『LeadGrid』を開発しています!
早速ですが、最近話題の「Claude Code」をみなさんは使いこなせていますか?
リリースされてから比較的すぐに使い始めた私は、どんなふうに使うといいかがわかってきました。そこで今回は、Claude Codeで「できること・できないこと・できるようになること」をご紹介しようと思います!
成田 陽紀(なりた はるき):2001年生まれ。そろばん1級(全国珠算教育連盟・日本珠算連盟)。学生時代は、株式会社GIGにインターンとして所属。2024年4月に株式会社GIGに入社。現在はLeadGrid開発チームにてエンジニアとして働いている。とても足が速い。
Claude Code、どこまでできる?
Claude Codeを実際に3ヶ月間使ってみて、どんなことが得意なのかが見えてきたのでご紹介します。
Claude Codeの得意なこと
・新しいファイルを作成するような作業
3ヶ月間使用して私が感じた、Claude Codeの一番の強みは「0-1の速さ」です。体感として、新しいファイルを作成するような作業は基本的にそこそこできます。とくに新しくアプリケーションを作る際の環境構築や、新しいライブラリの導入などではClaude Codeを信用して使っています。
・リプレイス
ライブラリ置き換えなどのリファクタリングも得意なことの一つです。簡単な単純作業の繰り返しのようなタスクは、Claude CodeのようなAIの得意分野であり、信頼して使うことができています。
・バックエンド
仕様が明確に決まっていることの多いバックエンドのタスクは、非常に得意だと感じます。「この入力形式に対し、ある点を考慮しつつ、このような出力をする」といった具体的な指示を出すことで、質の高いコードを書いてくれることが多いように感じます。
(現時点での)Claude Codeの限界
AIの進化は目覚ましいものがありますが、現時点でのClaude Codeには明確な限界も存在します。
・コードの質
とくに気になるのが「コードの質」です。この問題は、とくにフロントエンド開発に顕著に出てきます。たとえばReactでフロントエンド開発を頼んだ場合、一見動いているように作ってはくれるのですが、コードの中身を見ると、必要以上にuseEffectが使われていることが多々あります。
自分のプロンプトの問題もありそうですが、「useEffectをなるべく使わないように実装して」と依頼すると、かえってその部分を意識してしまい、質が低下してしまうことが多いように感じます。
・運用に対する意識の低さ
基本的にClaude Codeは運用に関することはあまり考えてくれません。何も言わないと、いろんな記法が混在したり、急にCSSをインラインで書き出したりしてしまいます。
こういった「コーディング規約」的なことは、CLAUDE.mdというファイルでClaude Code にプロジェクトの情報を伝えるはずなのですが、作業が長くなると、ついつい忘れられてしまうことが多いと感じます。
・検索機能の弱さ
Claude Code単体で使用していると、検索の弱さを感じることが多々あります。エンジニアとしては、最新のドキュメントを参照して欲しいときが多いかと思いますが、Claude Codeの検索はあまり強くありません。あくまでおまけくらいに思っていた方がいいかな?というのが体感です。
Claude Codeに導入するとパフォーマンスが上がるツールを紹介!
ここまでClaude Codeの得意・不得意な点を述べてきました。Claude Codeは、総じて非常に素晴らしいツールであり、開発効率はかなり上がっています。ここではさらにClaude Codeの不得意な部分を補うための便利ツールをご紹介します。
Claude code hook
こちらはClaude Code自体が用意してくれている機能です。Claude code hookについて、公式ドキュメントから引用すると
Claude Codeフックは、Claude Codeのライフサイクルのさまざまなポイントで実行されるユーザー定義のシェルコマンドです。フックは、Claude Codeの動作に対する決定論的な制御を提供し、LLMが実行を選択することに依存するのではなく、特定のアクションが常に実行されることを保証します。
とのことです。
だいぶ難しい日本語ですが、噛み砕くとClaude Codeのライフサイクルのたびに何かを発火することができるようになるよ、と言った感じです。
私は、Claude Codeが途中で確認を求めてきたり、作業が終わったタイミングで通知するようにしています。この通知は、長いタスクの間に連絡を返せたりしてとても便利だと感じています。他にも色々なライフサイクルが定義されているので、公式ドキュメントを参考にぜひ導入してみてください。
https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/hooks-guide
Context7
Context7はAI向けに書かれたドキュメントが揃っているMCPサーバーです。先の「Claude Codeの限界」の部分で記載した、「検索が弱い」という部分を補ってくれるツールです。
なんと、主要なライブラリやフレームワークなどのドキュメントがAIにとって読みやすい形でまとまっているMCPサーバーです(Context7に掲載されているプロジェクトは、Context7ではなく、それぞれの所有者によって開発および保守されているとのことで本当に感謝しています......)。Claude CodeにContext7を活用してもらうことで、最新のドキュメントを解像度高く参照してもらうことができます。
こちらに簡単な導入方法をご紹介します(APIキーの追加はオプションですが、APIキーを取得する方がメリットが多いため、ここでは推奨いたします)。
1. https://context7.comにアクセスし、適当なアカウントを作成しログインする。
2. https://context7.com/dashboard に移動し、APIキーを取得する。
3. claude mcp add context7 -- npx -y @upstash/context7-mcp --api-key {取得したAPIキーをここに貼り付ける} (インストール場所には、グローバルとプロジェクトディレクトリがあるため、ご注意ください)
4. claude mcp list でContext7が表示されていたら成功です。
これでContext7が使用できるようになりました。Cotext7を使用して欲しいときは、プロンプトに「use context7」と追記する必要があります。
https://github.com/upstash/context7
Readabirity MCP
最後にご紹介するツールは、Readabirity MCPです。こちらは、readability.js(https://github.com/mozilla/readability)というライブラリです。
readability.jsは、HTMLから本文を抽出するライブラリです。たとえば記事のURLを渡してをAIに読んでもらうとき、記事のページには、内容以外にもさまざまな情報が含まれています。
readability.jsを使うことで、本文のみを抽出してAIに渡すことができます。URLを投げるだけでも理解してくれることが多いですが、理解してくれない記事などをClaude Codeに渡すときは、使用してみることをおすすめします!
https://github.com/mizchi/readability
(まだ)AIは魔法ではなくて道具
Claude Codeについて、まとめてみましたがいかがでしたでしょうか?
AI関連のニュースは日々目まぐるしく更新されていき、一年前を思い返すと状況はまるで変わりました。
エンジニアにとって、Claude Codeはその筆頭ですね。うまく使うことで作業を超効率的に行えるようになりました。しかし、まだまだ人間と比べるとできないことも多く、「魔法ではなく道具」という領域かなと思います。引き続きAIの動向を注視しつつ、おいていかれないように頑張っていきましょう!
現在、GIGではエンジニアを募集中です!GIGでは、最新のAI情報を常にキャッチアップし続け、いいツールはどんどん導入しています!Webアプリケーション開発や、AIを使った開発に興味がある方のご応募をお待ちしております!
■株式会社GIG
お問い合わせはこちら
採用応募はこちら(GIG採用サイト)
採用応募はこちら(Wantedly)
WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

成田 陽紀
2001年生まれ。そろばん1級(全国珠算教育連盟・日本珠算連盟)。学生時代は、株式会社GIGにインターンとして所属。2024年4月に株式会社GIGに入社。現在はLeadGrid開発チームにてエンジニアとして働いている。とても足が速い。