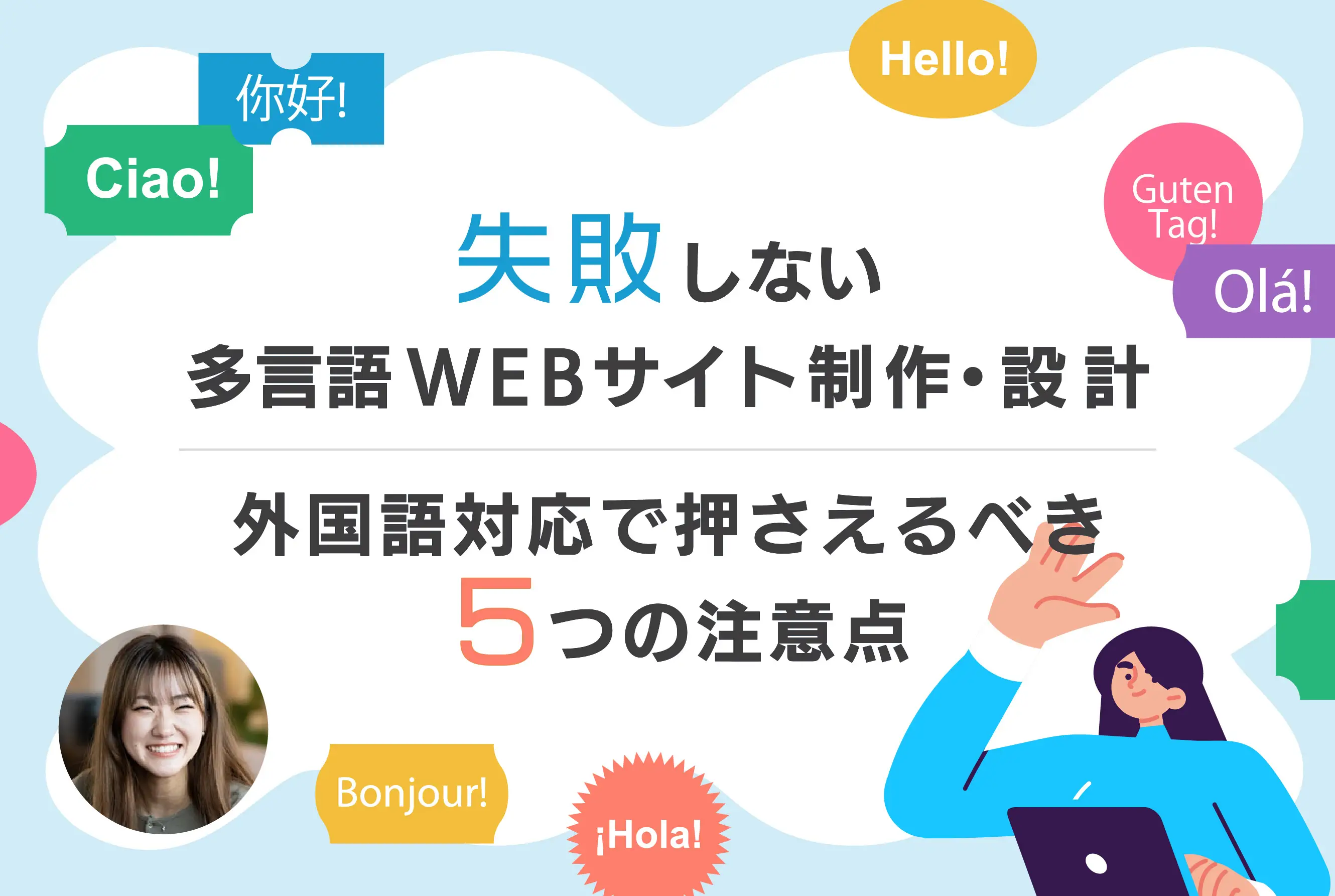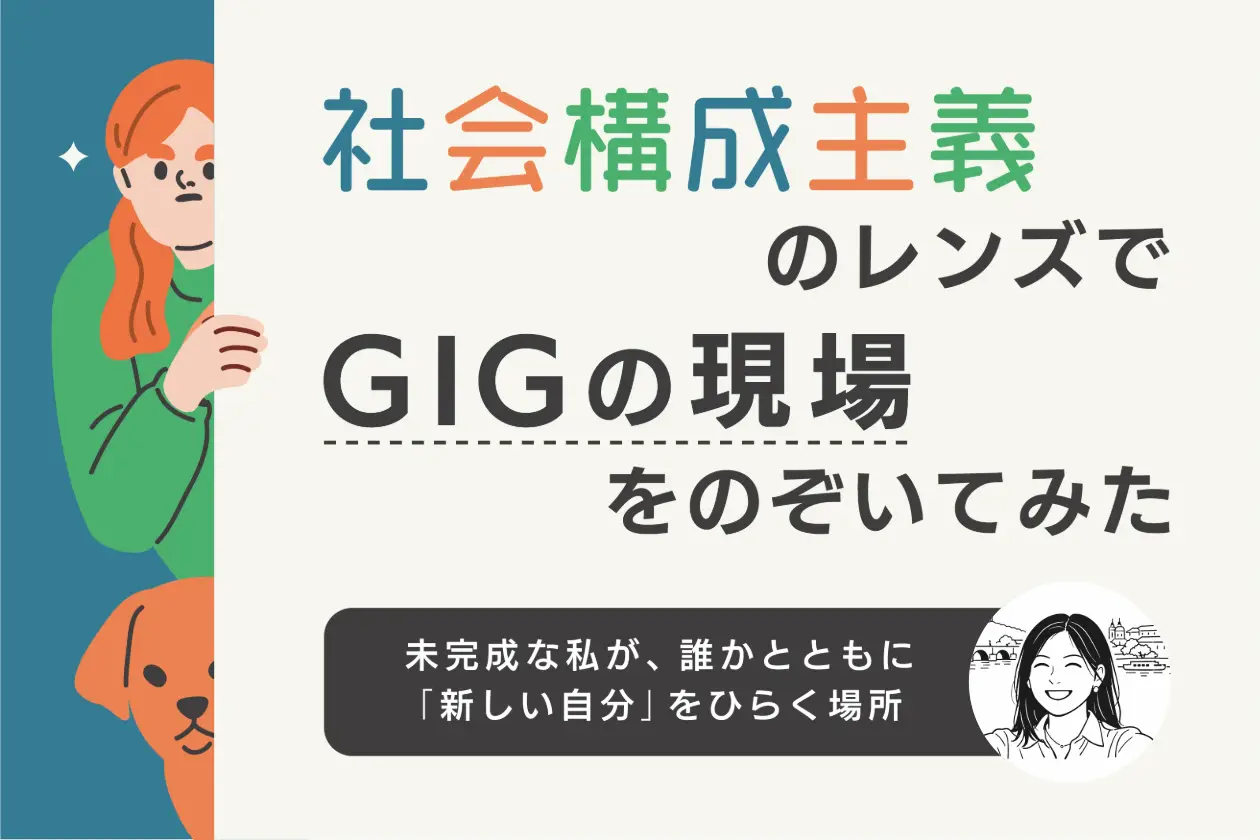インタビュー記事の3つの種類|対談・一人称・ルポ形式の違いと選び方|東京のWEB制作会社・ホームページ制作会社|株式会社GIG
BLOG
ブログ
インタビュー記事の3つの種類|対談・一人称・ルポ形式の違いと選び方
2025-03-26 制作・開発
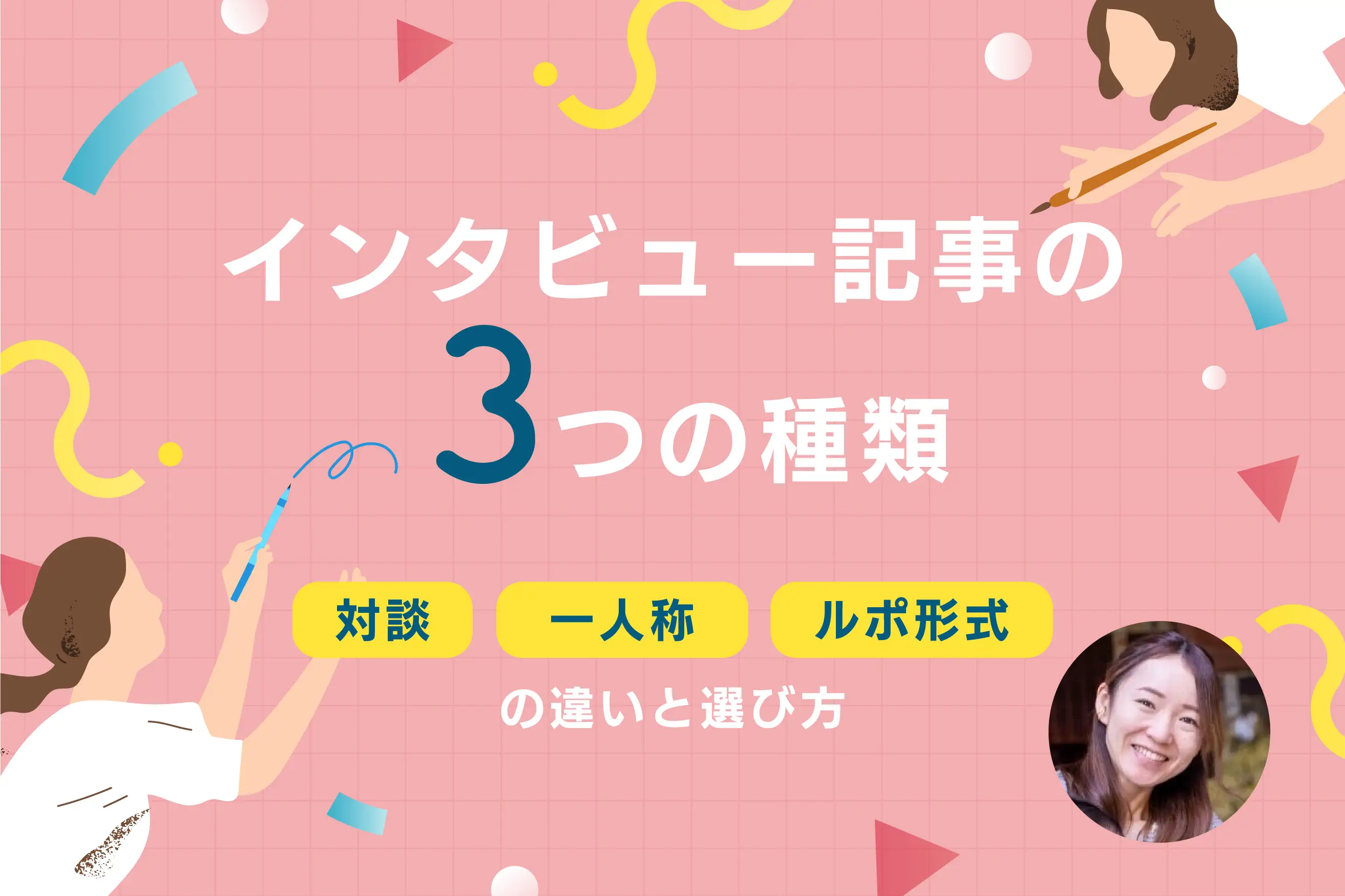
こんにちは、GIGでオウンドメディアの記事制作を担当している熊澤です。ライター歴7年。これまでに200本以上の記事制作を担当し、読者に届く文章づくりを追求しています!
オウンドメディアの記事を企画するとき、「インタビューを取り入れたいけれど、どんな書き方がベストかわからない」「インタビュー記事って、Q&A方式以外にあるの?」と、迷った方も多いのではないでしょうか。
インタビュー記事には対談・一人称・三人称(ルポ)の3種類があり、適切な形式を選ぶことで、読者の関心を引きやすくなります。
この記事では、それぞれの特徴や活用法を解説します。具体例も紹介しますので記事の方向性に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
インタビュー記事とは?オウンドメディアで活用すべき理由
インタビュー記事とは、取材を通じてリアルな声を届ける記事のことです。オウンドメディアにインタビュー記事が適している理由は、読者の共感や信頼を得やすく、企業の価値を自然に届けられるからです。
たとえば、どんなに優れたサービスを開発しても、企業の担当者が「これは本当に良い商品です!」と伝えるだけではリアリティーに欠け、「本当に役立つの?」と読者に疑問を持たれるかもしれません。
また、採用活動においても同様です。企業文化や職場の雰囲気を伝えたいとき、公式な会社説明だけではイメージがしにくく、実際の働き方や社員のリアルな声が届きにくい場合があります。
そんなときに役立つのがインタビュー記事です。オウンドメディアに取り入れると、企業の想いやサービスの価値が伝わりやすくなり、関心を引きやすくなります。具体的には、以下のような記事の切り口が効果的です。
| インタビューの切り口 | 効果 |
|---|---|
| 導入事例インタビュー | 実際にサービスを活用した顧客の声を伝え、信頼感を高める |
| 経営者インタビュー | 企業のビジョンや価値観を発信し、ブランドの魅力を伝える |
| 若手社員インタビュー | 入社後のリアルな経験を紹介し、求職者の不安を解消する |
インタビュー記事の代表的な3つの種類と特徴
インタビュー記事には目的や内容に応じた形式があり、「対談(Q&A方式)」「一人称(ストーリー形式)」「三人称(ルポ)」の3つが代表的です。
どの形式を選ぶかによって、記事の雰囲気や伝わり方が大きく変わります。
・対談形式(Q&A方式)
会話の流れが整理されるため、読者に意図を伝えやすい
・一人称形式(ストーリー形式)
物語のような流れで、読者が感情移入しやすい
・三人称(ルポ)形式
記者目線の客観性を大切にしながら、インタビュー対象者の声を活かす
そのため、「伝えたいこと × 読者にどう感じてほしいか」を考えながら、目的に合ったものを選びましょう。それぞれの特徴や活用シーンを詳しく解説していきます。
1.対談形式(Q&A方式)
対談形式は、2人以上が会話を交わしながら進めるインタビュー記事です。Q&A方式とも呼ばれ、インタビュアー(聞き手)が質問し、インタビュイー(話し手)が回答する形で構成されます。
【メリット】
・テンポが良く、読みやすい
会話がキャッチボールのように進むため、読者が飽きにくい
・異なる視点を取り入れられる
2人以上が話すことで、多角的な意見や考えがわかる
・企業の文化や雰囲気を伝えやすい
何気ない会話を通じて、社風や働き方が伝わる
【デメリット】
・会話が長くなると要点がぼやけやすい
話の流れを整理しないと、情報が散漫になりやすい
・話し手の個性が強すぎると読みにくいことがある
口語表現や冗長な部分は編集が必要
より具体的にイメージするために、メリット・デメリットがそれぞれ象徴された例を見ていきましょう。
テーマ:「新サービスの開発について」
【良い例】
インタビュアー:新しいプロジェクトの開発経緯について教えてください。Aさん:このプロジェクトは、社内で「業務をもっと効率化できないか?」という課題が浮上したことから始まりました。最初は既存のシステム改良を検討しましたが、現場の声を聞くうちに、それだけでは解決できないと気づいたんです。
【悪い例】
インタビュアー:新しいプロジェクトの開発経緯について教えてください。Aさん:いや〜、ほんと大変でしたよ!最初の企画案がボツになったときは、「あぁ、終わったな…」って思いましたね(笑)。でも、そこからチームでめちゃくちゃ議論して、あーでもないこーでもないってやって、最終的に今の形に落ち着いたんですよ!
話し手の口語表現をそのまま書くと、親しみやすさは出ますが、情報が曖昧になり、読者に正確な内容が伝わりにくくなるので注意が必要です。
2.一人称形式(ストーリー形式)
取材対象者が自身の経験や考えを語る形式です。話し手の視点でストーリーが展開されるため、読者はまるで本人の経験を追体験するように記事を読めます。
【メリット】
・深みのある内容になりやすい
一人の人物の視点に集中するため、ストーリーに没入しやすい
・読者の共感を生みやすい
具体的な経験談やエピソードを交えることで感情に響く
・ブランドストーリーを伝えるのに最適
企業の背景や想いを伝えるのに適している
【デメリット】
・取材対象者の話し方や語彙に依存する
表現力が乏しい場合、読者に伝わりにくい
・文章の流れを工夫しないと単調になりがち
時系列やエピソードの配置を工夫する必要がある
こちらも、良い例と悪い例を解説します。
テーマ:「キャリア転機について語る社員インタビュー」
【良い例】
私はもともと広告代理店で働いていましたが、「もっと自分の力で企画を動かしたい」と思い、現在の会社に転職しました。最初は業界も違い、右も左もわからない状態でしたが、今では自分の提案が採用され、チームの中心としてプロジェクトを動かす立場になっています。【悪い例】
私は、今の会社に入る前はまったく違う業界で働いていました。最初は「とにかくやってみよう!」と思って転職したんですが、いざ働き始めると、「あれ?思ってたのと違うかも…」って思うことが増えてきて(笑)。でも、まあ、やるしかないですよね。そんな感じで毎日バタバタしてたんです。
読者がストーリーに没入できるかどうかは、文章の流れやエピソードの選び方次第。語り口の自然さを活かしつつ、要点を明確にすることが大切です。
3.三人称(ルポ)形式
インタビュアーが取材対象者の話を、客観的な視点でまとめるレポート形式の記事です。話をそのまま伝えるのではなく、インタビュアー自身の視点や分析を交えながら、読者にわかりやすく整理します。
【メリット】
・第三者の視点で、事実を整理しながら伝えられる
読者が客観的に情報を理解できる
・社会的な意義のあるテーマに向いている
企業のCSR活動や業界の課題解決事例などに最適
【デメリット】
・記者の解釈が入るため、取材対象者の意図を正しく伝える工夫が必要
取材内容を編集する際に、誤解を生まないよう注意
・インタビュー対象者の個性が薄れがち
取材対象者の感情やストーリーが直接伝わりにくい
それぞれ良い例と悪い例を紹介します。
テーマ:「社内DXプロジェクトの裏側インタビュー」
【良い例】
社内DXプロジェクトが始動し、半年が経過した。プロジェクト管理ツールとワークフローシステムの導入により、社内の承認フローは50%短縮され、会議回数も減少した。しかし、一部の部門では「既存の業務フローに合わない」との指摘もある。Aさんは「導入がゴールではなく、現場の声をもとにした継続的な改善が大切」と話す。今後は、実際の運用データをもとにさらなる最適化を進める方針だ。
【悪い例】
社内DXプロジェクトが進行中だ。Aさんによると、デジタルツールの導入により、業務効率が改善していると言う。社員の多くが活用しており、社内の業務フローもスムーズになったようだ。一方で、一部の部門では「慣れるのに時間がかかる」との声もある。しかし、Aさんは「導入は成功している」と話し、今後はより使いやすい環境を整える考えだ。
読者が知りたいのは「何が起こったか」だけでなく、「なぜそうなったのか」。背景や経緯、具体的な数値も丁寧に補足し、より理解を深められる記事に仕上げましょう。
目的別!インタビュー記事の種類を選ぶコツ
インタビュー記事の種類は、オウンドメディアやコンテンツの目的に合わせて決定します。「誰に」「何を」届けたいのかを意識するのがポイント。パターン別におすすめの形式を紹介します。
社内文化や働き方の魅力をストレートに伝えたいなら「対談形式」
職場の雰囲気や社員のリアルな声を伝えるなら、対談形式が向いています。会話を通じて自然なやりとりを届けられるため、採用活動や企業ブランディングに役立ちます。
たとえば、社員同士のやりとりから、社風や働きがいを表現できますし、経営者の対談なら、成長戦略やビジョンを熱く伝えられます。さらに、他部署のリーダーが意見を交えるコラボ対談では、社内の連携やチームワークを魅力的にアピールできるでしょう。
読者の共感を生みたいなら「一人称形式(ストーリー形式)」
読者にぐっと寄り添い、感情を動かすストーリーを伝えるなら、一人称形式が効果的です。たとえば、創業者インタビューでは、起業のきっかけや挑戦のエピソードを語ることで、企業の想いや背景がよりリアルに伝わります。
また、商品やサービスの誕生秘話を紹介すれば、開発者のこだわりや試行錯誤が読者の共感を呼びやすくなります。ストーリー性のある記事は、読んだ後も心に残りやすいのが魅力です。
客観的に商品や成功事例を伝えたいなら「三人称(ルポ)形式」
「この商品、実際どうなの?」そんな読者の疑問には、三人称(ルポ)形式が役立ちます。
たとえば、導入事例なら、企業がサービスをどう活用し、どんな成果を生んだのかをレポート形式で紹介。ユーザーの声を交えれば、単なる自社PRではなく、読者に納得感を与えやすくなります。
新商品の紹介記事では、使用感や他製品との違いをデータや実例とともに伝えることで、独自性のある内容に。企業目線だけでなく、第三者の評価を加えると、より説得力のある記事になります。
メディアに合ったインタビュー記事の種類を選ぼう
一言に「インタビュー記事」といっても、対談・一人称・三人称と、形式はさまざまです。それぞれ特徴が異なるため、オウンドメディアの目的や読者層に合わせて適切な形式を選んでみてください。
執筆活動を通じて思うのは、どんなに素敵な話を聞いても、伝え方ひとつで読者の受け取り方がガラッと変わるということです。せっかく素敵なエピソードを聞いたのに、それをインタビュアーだけしか知らないのはもったいない…。人や商品、サービスの魅力を、読者にしっかり届けることがインタビュー記事の役割だと思います。
ただ話をまとめるだけではなく、「読者にどう伝わるか?」を意識して形式を選び、読者に届くインタビュー記事を作っていきましょう。
GIGでは、オウンドメディアの企画・取材・記事制作を一貫してサポート。企業の魅力やサービスの価値を、読者に届けるインタビュー記事づくりをお手伝いしています。
「どの形式が自社のメディアに合うのかわからない」「そもそも取材が不安」「もっと読まれるコンテンツにしたい」といったお悩みがあれば、ぜひご相談ください。目的やターゲットに合わせた最適な形式をご提案し、読者に届くストーリーを形にします。
■株式会社GIG
お問い合わせはこちら
採用応募はこちら(GIG採用サイト)
採用応募はこちら(Wantedly)
WebやDXの課題、無料コンサル受付中!

熊澤 南
大学時代は文学部社会学を専攻。卒業後、民間企業の人事部で採用・教育に携わる。2017年よりライター業を開始し、フリーランスとしても活動。2024年に株式会社GIGへジョイン。現在はマーケティング事業部に所属し、取材や導入事例記事などのコンテンツ制作を担当する。